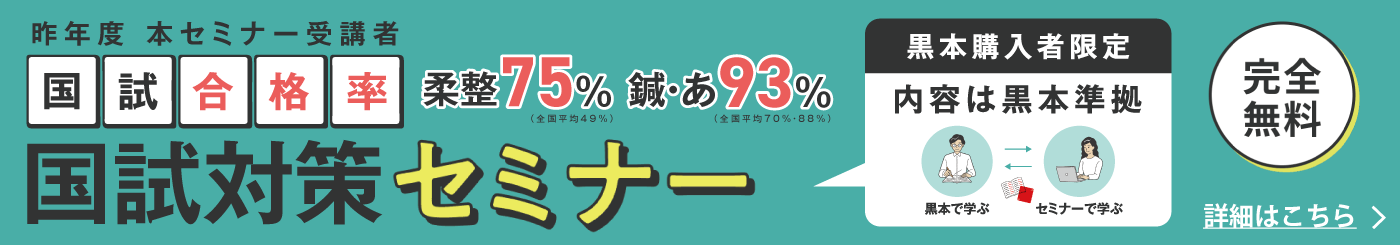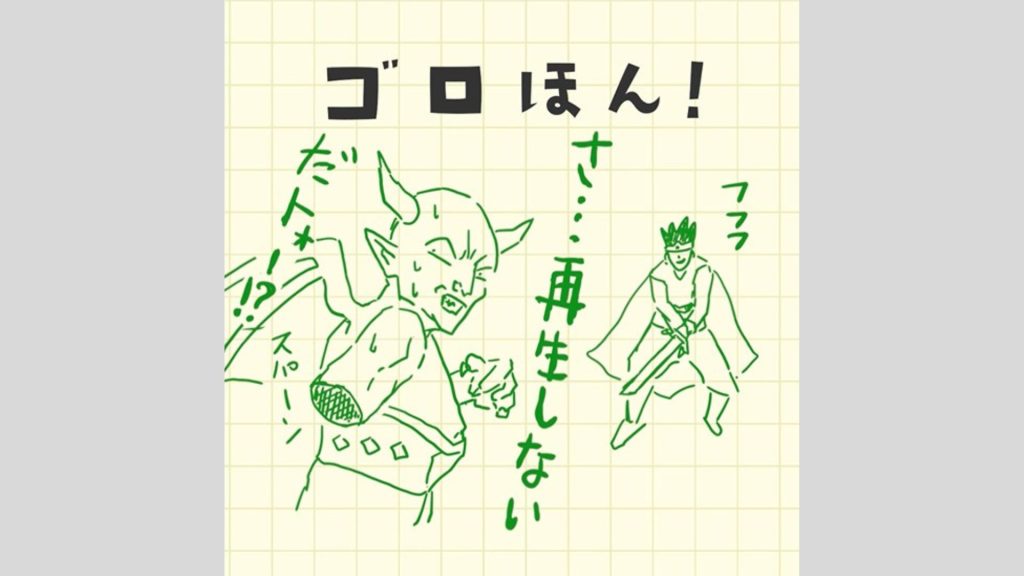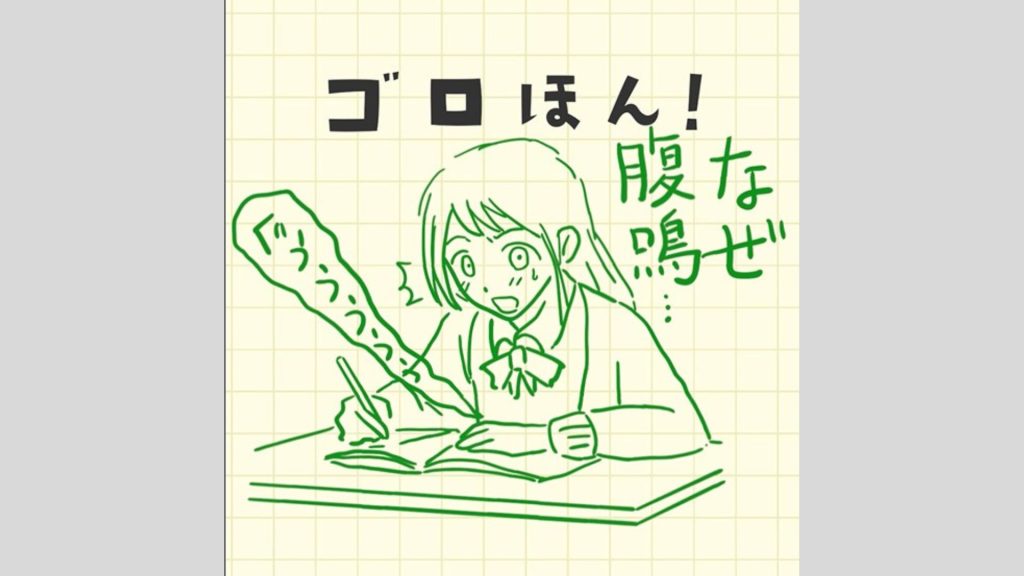五行色体表とは?五行色体表まとめ
国試対策・勉強
五行論とは
自然界におこる森羅万象を代表的な5つ「木」「火」「土」「金」「水」に分類した東洋哲学の一つです。
この5つの属性を五行と呼びます。
これらはお互いに助け合ったり、また抑制しあうことで自然界においてバランスを保っていると考えられています。
人間も自然界の中の一部として捉え、身体を「木」「火」「土」「金」「水」に分類することで、私たちの身体の状態を捉えるといった考え方です。
五行色体表とは
自然界においておこる現象を分類したこの五行に、世の中の物を分類してまとめたものがこの五行色体表と言えます。
例えば身近で耳にする言葉の一つとして、五臓六腑の「五臓」が挙げられます。
五行論における五臓では「木=肝臓」「火=心臓」「土=脾臓」「金=肺」「水=腎臓」と割り振られています。
そのほかにも五腑であれば「木=肝」「火=心」「土=脾」「金=肺」「水=腎」、季節であれば「木=春」「火=夏」「土=長夏」「金=秋」「水=冬」と5つに分類することで、今起きている現象を説明付け用としています。
色体表の活用方法
東洋医学の診断法のひとつとして、病態をおおまかに捉えるときに用いる分類法として活用することが出来ます。
実際の身体で考えてみた際に、自身の体質が五行のどこに属するか、また近しいかを調べていくことで、関連していそうな愁訴や症状等を見つけ出すことが出来るのです。
例えば目の霞みのような目の症状が出現したとします。
「目」は「五官」でいうと「木」に属しているので、同じく「木」に所属する「肝」に症状があるかもしれないと考えます。
もしかしたら「涙(=五液)」が止まらなかったり、また「怒り(=五志)」っぽかったりするかもしれません。
まさに自然から身体まで様々な自然界におこる森羅万象を5つに分類し、類似するグループ同士を集めた五行色体表ならではの考え方の一つです。
実際の色体表(五行色体表)
←左右にスクロール可能→
まとめ
過去の鍼・灸・あん摩マッサージ指圧師試験では、この五行色体表は何度も問われています。
早いうちに五行色体表を覚えておけば、国家試験だけでなく臨床現場でも役に立つ場面が来るのではないでしょうか。