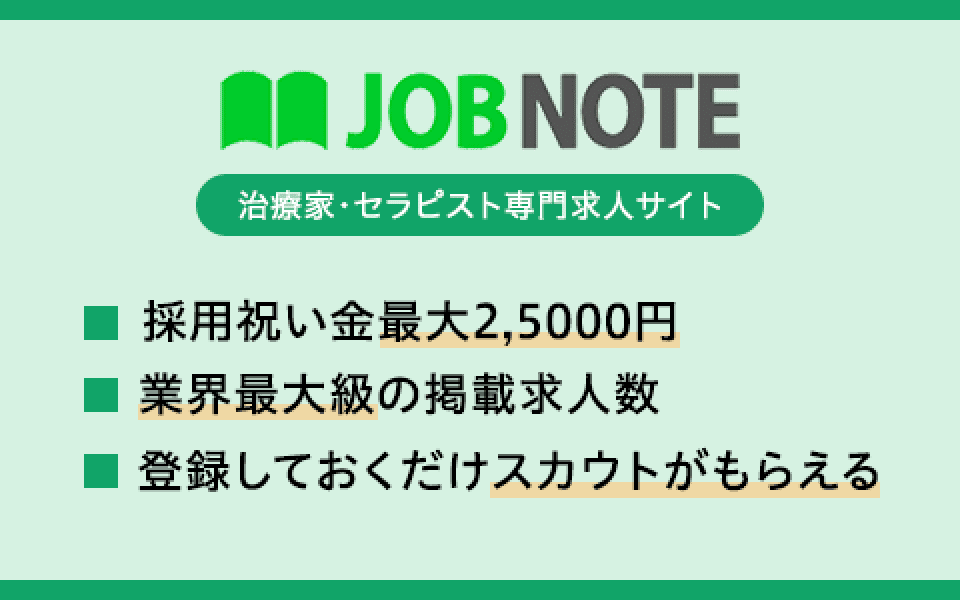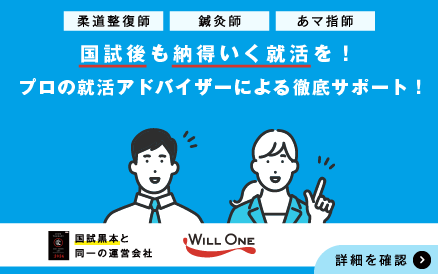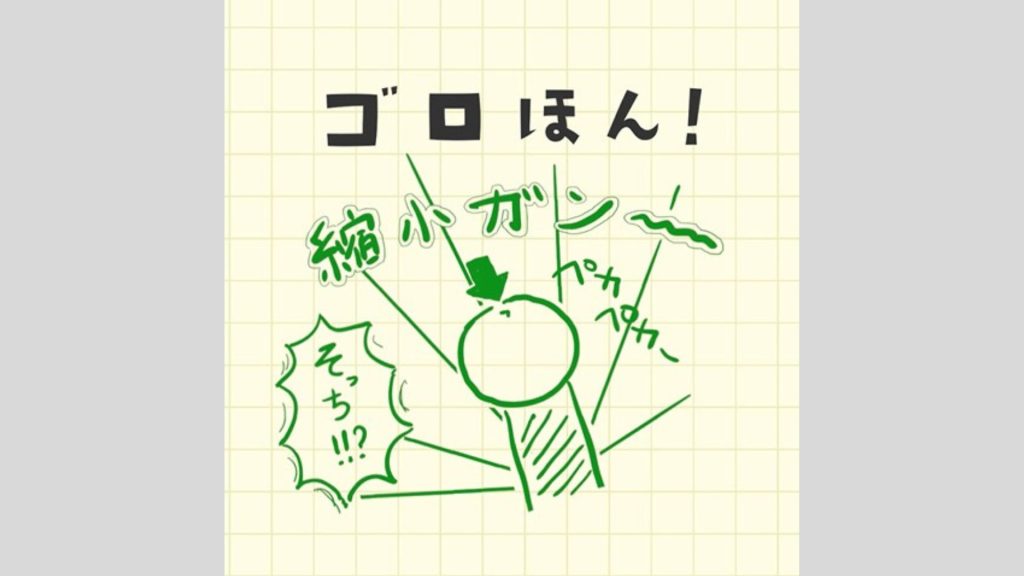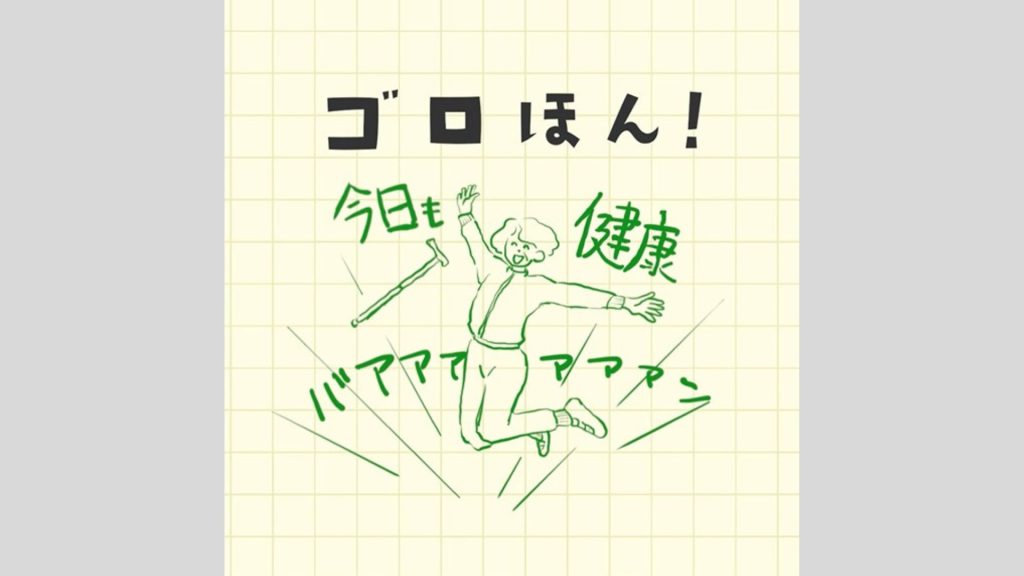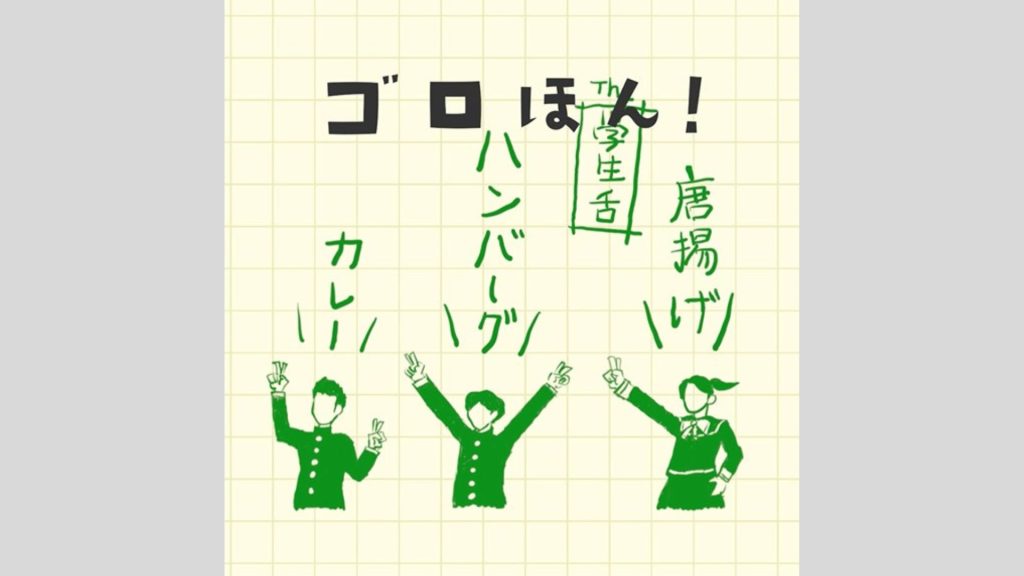『ゴロほん!』生理学まとめ~20秒で国試対策~
国試対策・勉強
このページに載っているゴロを暗記して、解剖学をマスターしよう♪
【国試対策のポイント】
イメージを持って覚えたほうが記憶に残りやすいので、絵や図にしてみるといいでしょう。できれば構造とその特徴、周囲との位置関係などを簡単な図にできるくらいにしておくのが理想です。
基礎科目では教科書の文章がそのまま問題文や選択肢に使われる出題が見られますので、教科書をしっかり読んで理解を深め、知識を増やしておきましょう。
※『ゴロほん!』は国試黒本の内容を基に制作しています。主に柔整編・鍼灸マッサージ編の両方に共通する科目から制作していますが、資格によって取り扱う語句が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※ゴロ動画内で掲載されている広告は動画公開時点のものです。ご視聴のタイミングによってはプロモーション期間対象外となる場合がございます。
神経系のゴロ
生体の内、外部環境からの刺激は眼、耳、鼻、舌、皮膚、筋、内臓などの感覚受容器を活動させます。そこで作られた情報は活動電位により中枢神経に伝わります。これらの感覚情報は、生体内外の環境を脳が反映させるために使われ、これにより行動が引き起こされます。感覚や記憶などの情報は運動行動や生体内の環境をもとに反射を制御します。この一連の流れは中枢神経の膨大なニューロンの活動とニューロン間での信号のやり取りで生じます。
- 「あっ/しょ~/きん!」で(Ⅱ群)感覚性ニューロンの機能を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「み/な/く/とう」で副交感神経線維を含む脳神経を覚えよう(黒本/柔整より)
運動系のゴロ
ヒトは運動神経からの伝達信号により常に何かの動作を行っており、骨格筋を常に収縮させています。運動は3つに分類することが出来ます。①熱いものに触れると手を無意識に引っ込める②歩行、咀嚼など終始は意識的だが生まれつき備わっており無意識に行われる③ある目的の為に意識的に行われるです。③は最初は意識的に行われる運動であっても、学習して無意識化されます。日常動作はこれらにより成り立ちます。
- 「し/お/きょ~/ふ」で皮膚反射の種類を覚えよう(黒本/鍼灸より)
内分泌系のゴロ
内分泌系は神経系と同様に生体機能の調節として働きます。内分泌系による生体機能の調節は内分泌腺から分泌されるホルモンによってなされます。神経系が主に迅速な調節を行うのに対し、内分泌系は主として緩慢ですが長期に渡るような調節を行います。
分泌が過剰になると上位のホルモン分泌細胞に作用しその働きを抑えます。
- 「び/す/こ」で脂溶性ホルモンの種類を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「かて!/ペプ/たん!」で水溶性ホルモンの種類を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「こう/ふく/まつ」でアミン型のホルモンを覚えよう(黒本/柔整より)
骨系のゴロ
骨は筋肉が付着することで骨格筋となり骨の内部に存在している骨髄は赤血球を産生し、骨から血中へCa²⁺の放出(骨吸収)と抑制、骨形成の促進をおこない骨組織の細胞の働きを促すほか多くの重要な機能の調節に関与します。
また、形態的に体の各単位の質量や大きさがそれぞれ増加したり機能的に成熟するために必要です。
- 「じょう/かる/び」で骨の再吸収と再形成に関わるホルモンを覚えよう(黒本/柔整より)
尿の生成と排泄系のゴロ
腎臓は尿を生成し、体液の量や電解質、その他の種々の物質の濃度を調節する働きを持ちます。腎臓で生成された尿は、尿管を通って膀胱に送られ、膀胱に一時貯められたのち、尿道を通って排出されます。尿は淡黄色をした液で、約95%を水が占めます。
比重は約1.003~1.030で、体液の液状が一定になるように排出されるので、その組成は種々の条件(食事、水分や塩分の摂取量、運動量、気温など)によって変化します。
- 「た/ぐる/あみ」で尿に含まれないものを覚えよう(黒本/柔整より)
まとめ
今後も国試対策に役に立つゴロ動画を随時追加していきます♪
公式SNSでも更新のお知らせをしているので、ぜひフォローして更新をお待ちくださいね♪
ゴロほん!と一緒に目指せ!国試合格🌸