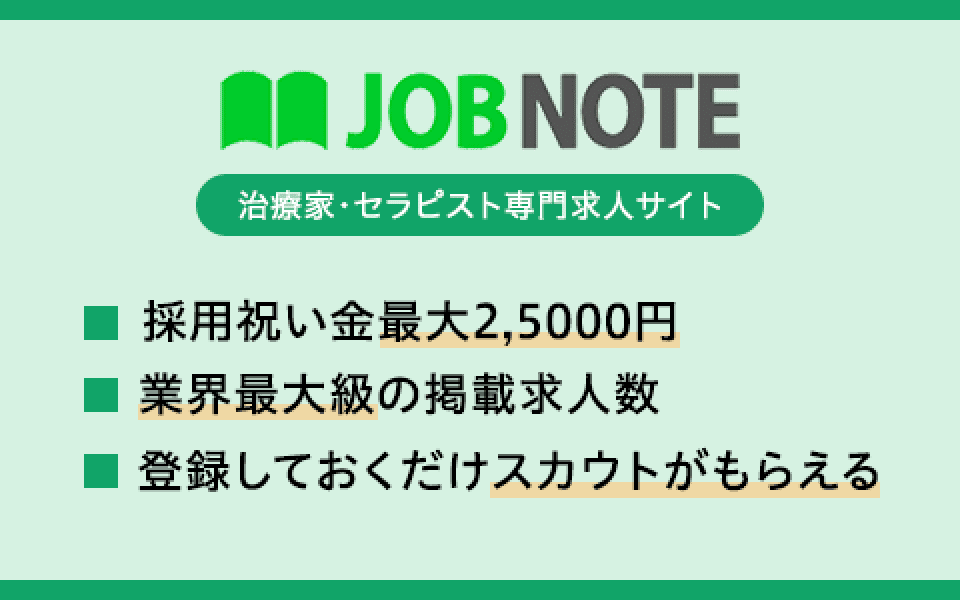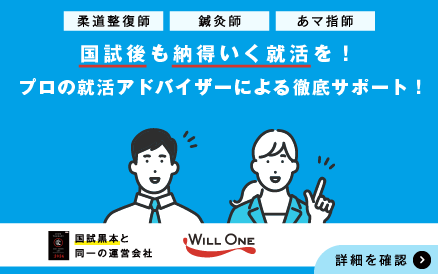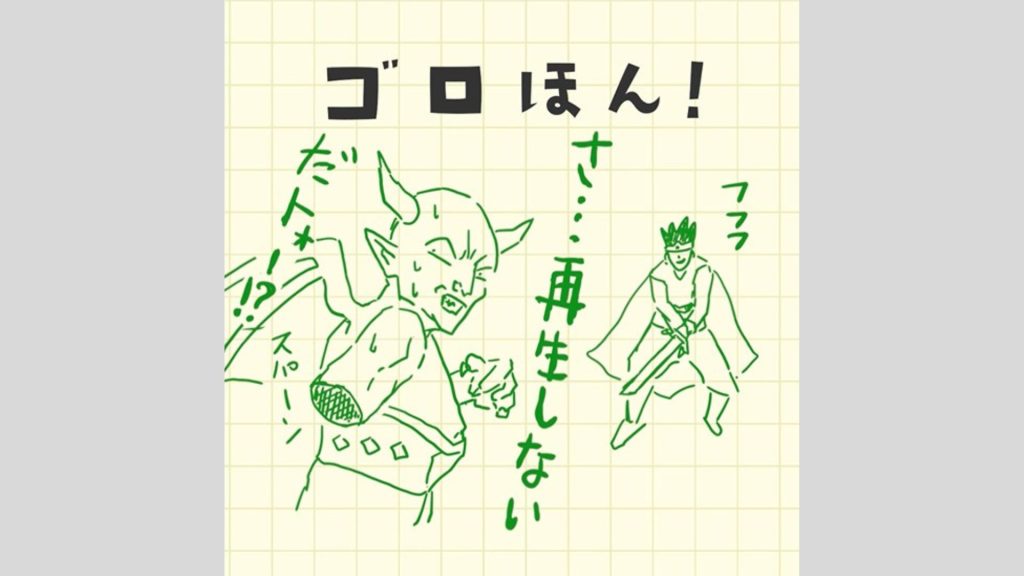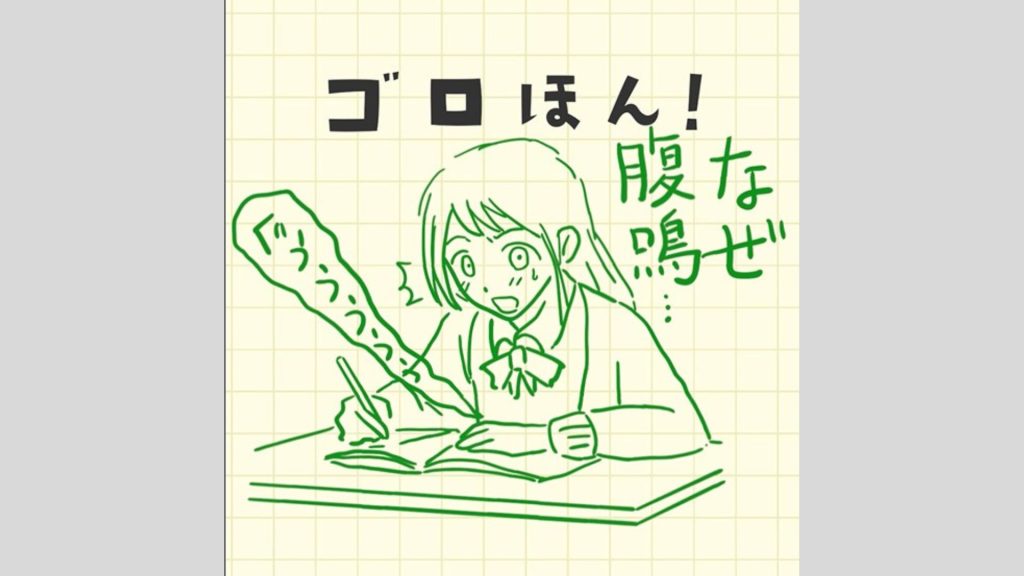『ゴロほん!』解剖学まとめ~20秒で国試対策~
国試対策・勉強
このページに載っているゴロを暗記して、解剖学をマスターしよう♪
【国試対策のポイント】
イメージを持って覚えたほうが記憶に残りやすいので、絵や図にしてみるといいでしょう。できれば構造とその特徴、周囲との位置関係などを簡単な図にできるくらいにしておくのが理想です。
基礎科目では教科書の文章がそのまま問題文や選択肢に使われる出題が見られますので、教科書をしっかり読んで理解を深め、知識を増やしておきましょう。
※『ゴロほん!』は国試黒本の内容を基に制作しています。主に柔整編・鍼灸マッサージ編の両方に共通する科目から制作していますが、資格によって取り扱う語句が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※ゴロ動画内で掲載されている広告は動画公開時点のものです。ご視聴のタイミングによってはプロモーション期間対象外となる場合がございます。
人体解剖学概説のゴロ
医学における解剖学は人体解剖学を指しますが、人体の形態や構造も、他の生物体と同様、生物学的法則性に支配されてつくられたものです。解剖学は、生物体の形態と構造の奥に隠された法則性を発見し、これらの形態的現象を整理し、系統立てるところにその目的があります。
しっかりおさえて得点アップを目指しましょう!
- 「ひ/しん/かん」で外胚葉から分化するものを覚えよう(黒本/柔整より)
- 「き/らん/びくっ!」で多列線毛上皮の部位を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「つ/ち/やわっ!」で線維軟骨がつくるものを覚えよう(黒本/柔整より)
- 「じか/び/がい/こう」で弾性軟骨がつくるものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「筋系/泌尿・生殖器系/脈管系/骨格系」で中胚葉から分化するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「尿路/消化器/呼吸器」で内胚葉から分化するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
骨格系のゴロ
骨格系は運動器としての機能のほかに中枢神経や内臓の保護器官として重要です。人体全体および各部の形を維持する支柱としての意義も大きく、血球の生産を続ける赤色骨髄組織が胸郭や骨盤の骨の中にあります。また、骨質はリン酸カルシウムを大量に含むため、血液のリン酸とカルシウムの濃度を一定に保つ貯水池としての意義も重要です。
- 「つい/ふく/えん」で大後頭孔を通るものを覚えよう(黒本/柔整より)
- 「かた!/ワン/コ」で球関節に分類される関節を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「び/かん/せん」で骨盤の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「しゅ/げ/さんかく/まめ!」で手根骨近位列を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「きょ~/かかと/しゅう/り」で横足根関節の構成を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「がんか/きょう/か」で下眼窩裂を通過するものを覚えよう(黒本/柔整より)
- 「にゅう/ふく/ろ」で椎骨のうち腰椎特有の突起を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「きょ~/けい/ひ」で距腿関節の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「ぜんご/しょ~/さん」で距腿関節を補強する靭帯を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「イチロ/きょう/いっき」で胸郭上口の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「いに/いい/け/ろ」で胸郭下口の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「だい/しょう/あり/あり」で手根骨遠位列(橈側から)を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「迷路動脈/顔面神経/内耳神経」で内耳孔を通過するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
筋系のゴロ
運動器としての筋は骨格筋線維と結合組織からできており、筋線維はこれに付着する運動神経線維から信号を受けて収縮しますが、その収縮力は結合組織によって骨格系に伝えられ、関節を動かす等の運動を生じます。
筋組織は骨格筋、平滑筋、心筋の3種で構成されます。筋は運動器としての機能に加えて筋収縮に伴う体熱の発生およびリンパや静脈血を動かす筋ポンプとしても重要です。
- 「ちょ~/ほ/そ!」で大腿三角の構成(スカルパ三角)を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「そと/ちょ~/ひろい」で腰三角の構成を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「ほう?/はん/うす」で鵞足の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「ちょう/しん/せん/せい」で手根管を通過するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「きょう/せい/か!」で前頸三角の構成を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「さ/め/しょっく」で食道裂孔を通過するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「こう/きょう/か/き」で大動脈裂孔を通過するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「わん/えん/じょう」で肘窩の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「しょう/きょ/き/けん」で回旋筋腱板(ローテーターカフ)の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「ちゅう/し/しつ」で側副靱帯がある関節を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「腹横筋/外腹斜筋/内腹斜筋」で鼠径管の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「大腿神経/腸腰筋/大腿外側皮神経」で筋裂孔を通過するものを覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「顎二腹筋前腹/正中線/舌骨体」でオトガイ下三角の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「胸鎖乳突筋/肩甲舌骨筋/鎖骨」で大鎖骨上窩の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
脈管系のゴロ
体内にある体液(血液やリンパ)は全身を循環しており、血液を循環させる系統を血管系、各組織の中を潤すリンパを循環させる系統をリンパ系といいます。液体を通すこれらの系統は形態的に管状構造をとるので、総じて脈管系とも呼ばれます。脈管は主に体幹の脈管、上肢の脈管、下肢の脈管、頭頚部の脈管に区画できます。
- 「しん/じん/の/ひ」で機能的終動脈がみられる臓器を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「食道静脈/気管支静脈/上横隔膜静脈/肋間静脈」で奇静脈に注ぐ静脈を覚えよう(黒本/鍼灸より)
呼吸器のゴロ
ヒトは呼吸をすることでCO2を排出しO2を取り入れることで、体内のエネルギーバランスを保っています。肺は漿膜の1つである胸膜におおわれ、呼吸運動に伴う横隔膜と外肋間筋の収縮・弛緩によって肺内で外気の流入と呼出を繰り返しており、外気の空気と血液との間のガス交換を外呼吸(または肺呼吸)、血液と細胞との間のガス交換を内呼吸(または組織呼吸)とよんでいます。
- 「こうじ/こう/りん」で不対性の喉頭軟骨を覚えよう(黒本/柔整より)
泌尿器のゴロ
泌尿器は、血液中の老廃物や不用物質を尿として排泄する役割を持ち、腎臓、尿管、膀胱、尿道からなります。
腎臓では、尿の産生や水の再吸収、尿管/膀胱/尿道は産生された尿の通路としての役割を持ち、膀胱では貯留することができます。
- 「腎静脈/尿管/腎動脈」で腎門を出入りする主要な脈管を覚えよう(黒本/鍼灸より)
内分泌系のゴロ
分泌とは、細胞が特定の化学物質をつくって放出することであり、分泌を行う細胞の集まりを分泌腺といいます。分泌腺には外分泌腺と内分泌腺があり、外分泌腺では導管により分泌物は体外に放出されます。内分泌腺には導管がなく分泌物は毛細血管に入り血流により全身に運ばれます。
- 「まえ/ちゅう/りゅう」で腺性下垂体の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
神経系のゴロ
神経系は、神経細胞から伸び出る細かくて長い突起が集まった神経線維によって、一定の指令を伝達します。神経組織が集まって脊髄、そして脳をつくり、からだの各部分(末梢)からの刺激を受け取り、統合し調整した新しい興奮を末梢へ送り出します。中枢神経系、末梢神経系、自律神経系などがあります。
- 「かつ/ぜつ/が/ふく」で純運動性の脳神経を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「ワン/ツ/エイッ」で純感覚性の脳神経を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「かいば/たい/へん/かい?」で大脳辺縁系の構成を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「ちょう/きゅう/かん」で側頭葉の機能局在を覚えよう(黒本/柔整より)
- 「こう/ざ/じょう/げ」で仙骨神経叢の枝を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「ない/ない/ない/しゃ」で腕神経叢内側神経束の枝を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「れんず/びじょ/へ~/ぜん」で大脳基底核の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
感覚器のゴロ
感覚器系は外界の物理的または化学的刺激を受容する器官で、視覚器・平衡聴覚器・味覚器・嗅覚器がこれに属します。皮膚もまた感覚器の1つに数えられていますが、身体の機械的な保護と体温の調節等も行っています。
- 「つ/き/あぶる」で耳小骨の種類を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「か/ぜ!?/はぁ!?」で骨迷路の区分を覚えよう(黒本/鍼灸より)
循環器系のゴロ
循環器系とは、体内にある体液(血液やリンパ)を循環させる輸送系のことです。血液を循環させる系統を血管系、各組織の中を潤すリンパを循環させる系統をリンパ系といいます。液体を通すこれらの系統は形態的に管状構造をとるので、脈管系とも呼ばれます。体液が循環する際にポンプの役割を果たすのが心臓です。全身をめぐる循環を体循環(大循環)といい、心臓から肺をめぐる循環を肺循環(小循環)といいます。
- 「じょう/か/だい!」で大動脈の区分を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「腕頭動脈/左総頸動脈/左鎖骨下動脈」で大動脈弓から出る動脈を覚えよう(黒本/鍼灸より)
人体の構成のゴロ
人体を形づくる最初の単位は細胞です。これらの細胞は集合体となり”組織(上皮組織・結合組織・筋組織・神経組織)”を構成し、協同して一定の機能を営むために”器官”をいうかたまりをつくります。さらに、器官は協力して作業を営む一連の器官群によって器官系(運動器系(骨格系と筋系)、循環器系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、神経系、感覚器系)がつくられ、全体として調和・統一のとれた個体が形成されるのです。
- 「じ/し/けん」で密性結合組織を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「にょ/にょ/ぼう/じん」で移行上皮の部位を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「じゅっ/さい/じ」で神経細胞の構成を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「えき/こう/にゅう」で大汗腺(アポクリン汗腺)がある部位を覚えよう(黒本/鍼灸より)
消化器のゴロ
消化器は、口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肝臓、すい臓からなり、摂取した食物の栄養分を消化吸収し、老廃物を排泄するための器官です。
内臓が中空性器官、実質性器官に分かれるように、消化器も中空性臓器、実質性臓器に分けられます。
中空性臓器には食道から肛門までが含まれ、腔壁は粘膜、筋層、漿膜(外膜)の3層よりなります。
実質性臓器には肝臓・腎臓・膵臓などがあり、それぞれ臓器が機能するための細胞が主体となり、臓器を形成しています。
- 「内斜/中輪/外縦」で胃の筋層を覚えよう(黒本/鍼灸より)
- 「腹膜垂/結腸ヒモ /結腸膨起」で結腸の特徴的な構造を覚えよう(黒本/鍼灸より)
まとめ
今後も国試対策に役に立つゴロ動画を随時追加していきます♪
公式SNSでも更新のお知らせをしているので、ぜひフォローして更新をお待ちくださいね♪
ゴロほん!と一緒に目指せ!国試合格🌸